7月19日(金)
近年、高血圧の誘発原因として、
"塩は健康の敵"のように言われています。
しかし、果して本当にそうなのでしょうか。
塩は私たちの生命維持に欠かせない成分です。
では、どのくらいの量を摂取するのが望ましいのでしょうか。
今回は、塩の体内における役割や摂取量などについてお話しします。
「塩は体内で、主に細胞を保つ働きをしています
「塩」の正式名称は、塩化ナトリウム。
ナトリウム(Na)と塩素(Cl)が結合したものです。
塩を食べ物として取るときは、「食塩」と呼びます。
食塩には、純粋な精製塩(塩化ナトリウム99.5%以上含有)と
ほかのミネラルを含む自然塩があります。
食塩は、体の中に入るとナトリウムイオンと塩素イオンに分かれます。
そしてそれらは主に、「細胞外液」という、血漿や細胞の間を満たしている
液体の中に含まれます。
細胞外液は体重の約20%を占めており、ナトリウムイオンの50〜60%がここに
(30%は胃の中)、塩素イオンも大部分がここに含まれます。
この細胞外液は、細胞にとって海のような存在で、
細胞のひとつひとつが細胞外液の中に浮かんでいます。
塩はその中で、細胞外液の量と浸透圧を一定に保つ働きを
しています。つまり体には、一定量のナトリウムと塩素が
常に必要だということです。
ちなみに、体重70kgの成人は、体内にナトリウムと塩素を
合わせて200g程度保持しています。
ギリシャ・ローマ時代、通貨がなかったこの時代に通貨代わりに
使われたのが「塩」。塩は兵士たちの給与でした。
英語のサラリー(給与)は、ラテン語のサル(塩)からきた言葉です。
そして、中性ヨーロッパでは、宴会のテーブルには塩が置かれ、
身分の高い人は塩のそばに、身分の低い人は塩から離れて座る習慣
があったといいます。
それほど塩は貴重なものでした。人間の歴史において、塩が足りずに苦労した時代が
長かったのです。そうした経過を経たため、人間の食塩保持能力は高く、
塩を取り過ぎると、循環血液量が増えて血圧が上がります。
もちろん、すべての人の血圧が上がるわけではなく、食塩感受性がある人たち
(全体の25〜40%くらい)の血圧が上がります。
逆に、体内で食塩が不足した場合は「疲労、血圧の低下、立ちくらみ、
筋肉痙攣」などの症状が出ます。つまり、人間は体内に塩を必要とする
生き物であり、食塩欠乏に対して、強力な防御体質をもっているのです。
成人の1日当たりの食塩必要量は2g。これが生命保持のための必要量ですが、
現代人は概ね、その5〜10倍の量を摂取しています。
女性の7割が6〜13g、男性は食事量が多いので、その20%増しの7〜15g。
個人差はありますが、これが食事を美味しく楽しめる塩分量と言っても
いいかもしれません。
一般に、ストレスがかかると食塩摂取量は増えます。
また食事量(エネルギー)と食塩摂取量は比例する傾向にある
(※グラフ参照)ため、食事量を減らせば食塩摂取量も減りま
す。ダイエット中も食塩摂取量が減っていると言えます。
塩は人間の身体にとって必要なものです。
減塩は必要ですが、あまり神経質にならずに食生活を楽しんで
ください。塩分の取り過ぎかな?と思う方は、野菜をたっぷり
食べましょう。新鮮な野菜や果物には、カリウムが多く含まれ
ていて、余分なナトリウムを排出してくれる働きがあります。
もちろん、以下の方には減塩をおすすめします。
●高血圧の方
●家族に高血圧の人がいる方
●脳卒中を起こしたことのある方
●糖尿病の方
●心臓・腎臓に病気をもつ方
料理の味付けを工夫したり、ダシをきかせたりして塩分控えめに努めましょう。
食べ過ぎ、あるいは外食や加工食品が多い方は特に注意が必要です。
* * *
もうじき夏本番。水分と適度な塩分補給、バランスの良い食事で、
元氣に夏を乗り切りましょう!
(元氣通信 Vol.89より)
近年、高血圧の誘発原因として、
"塩は健康の敵"のように言われています。
しかし、果して本当にそうなのでしょうか。
塩は私たちの生命維持に欠かせない成分です。
では、どのくらいの量を摂取するのが望ましいのでしょうか。
今回は、塩の体内における役割や摂取量などについてお話しします。
「塩は体内で、主に細胞を保つ働きをしています
「塩」の正式名称は、塩化ナトリウム。
ナトリウム(Na)と塩素(Cl)が結合したものです。
塩を食べ物として取るときは、「食塩」と呼びます。
食塩には、純粋な精製塩(塩化ナトリウム99.5%以上含有)と
ほかのミネラルを含む自然塩があります。
食塩は、体の中に入るとナトリウムイオンと塩素イオンに分かれます。
そしてそれらは主に、「細胞外液」という、血漿や細胞の間を満たしている
液体の中に含まれます。
細胞外液は体重の約20%を占めており、ナトリウムイオンの50〜60%がここに
(30%は胃の中)、塩素イオンも大部分がここに含まれます。
この細胞外液は、細胞にとって海のような存在で、
細胞のひとつひとつが細胞外液の中に浮かんでいます。
塩はその中で、細胞外液の量と浸透圧を一定に保つ働きを
しています。つまり体には、一定量のナトリウムと塩素が
常に必要だということです。
ちなみに、体重70kgの成人は、体内にナトリウムと塩素を
合わせて200g程度保持しています。
ギリシャ・ローマ時代、通貨がなかったこの時代に通貨代わりに
使われたのが「塩」。塩は兵士たちの給与でした。
英語のサラリー(給与)は、ラテン語のサル(塩)からきた言葉です。
そして、中性ヨーロッパでは、宴会のテーブルには塩が置かれ、
身分の高い人は塩のそばに、身分の低い人は塩から離れて座る習慣
があったといいます。
それほど塩は貴重なものでした。人間の歴史において、塩が足りずに苦労した時代が
長かったのです。そうした経過を経たため、人間の食塩保持能力は高く、
塩を取り過ぎると、循環血液量が増えて血圧が上がります。
もちろん、すべての人の血圧が上がるわけではなく、食塩感受性がある人たち
(全体の25〜40%くらい)の血圧が上がります。
逆に、体内で食塩が不足した場合は「疲労、血圧の低下、立ちくらみ、
筋肉痙攣」などの症状が出ます。つまり、人間は体内に塩を必要とする
生き物であり、食塩欠乏に対して、強力な防御体質をもっているのです。
成人の1日当たりの食塩必要量は2g。これが生命保持のための必要量ですが、
現代人は概ね、その5〜10倍の量を摂取しています。
女性の7割が6〜13g、男性は食事量が多いので、その20%増しの7〜15g。
個人差はありますが、これが食事を美味しく楽しめる塩分量と言っても
いいかもしれません。
一般に、ストレスがかかると食塩摂取量は増えます。
また食事量(エネルギー)と食塩摂取量は比例する傾向にある
(※グラフ参照)ため、食事量を減らせば食塩摂取量も減りま
す。ダイエット中も食塩摂取量が減っていると言えます。
塩は人間の身体にとって必要なものです。
減塩は必要ですが、あまり神経質にならずに食生活を楽しんで
ください。塩分の取り過ぎかな?と思う方は、野菜をたっぷり
食べましょう。新鮮な野菜や果物には、カリウムが多く含まれ
ていて、余分なナトリウムを排出してくれる働きがあります。
もちろん、以下の方には減塩をおすすめします。
●高血圧の方
●家族に高血圧の人がいる方
●脳卒中を起こしたことのある方
●糖尿病の方
●心臓・腎臓に病気をもつ方
料理の味付けを工夫したり、ダシをきかせたりして塩分控えめに努めましょう。
食べ過ぎ、あるいは外食や加工食品が多い方は特に注意が必要です。
* * *
もうじき夏本番。水分と適度な塩分補給、バランスの良い食事で、
元氣に夏を乗り切りましょう!
(元氣通信 Vol.89より)


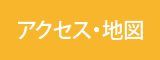
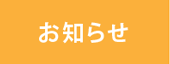

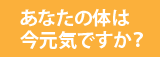


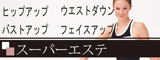


⇒ ライフマインド (09/07)
⇒ どちら様々 (09/05)
はがき絵
⇒ ライフマインド (08/27)
⇒ koyuki (08/20)
旅のスタート
⇒ ライフマインド (10/25)
⇒ 鳥栖のうどん大好き者 (10/24)